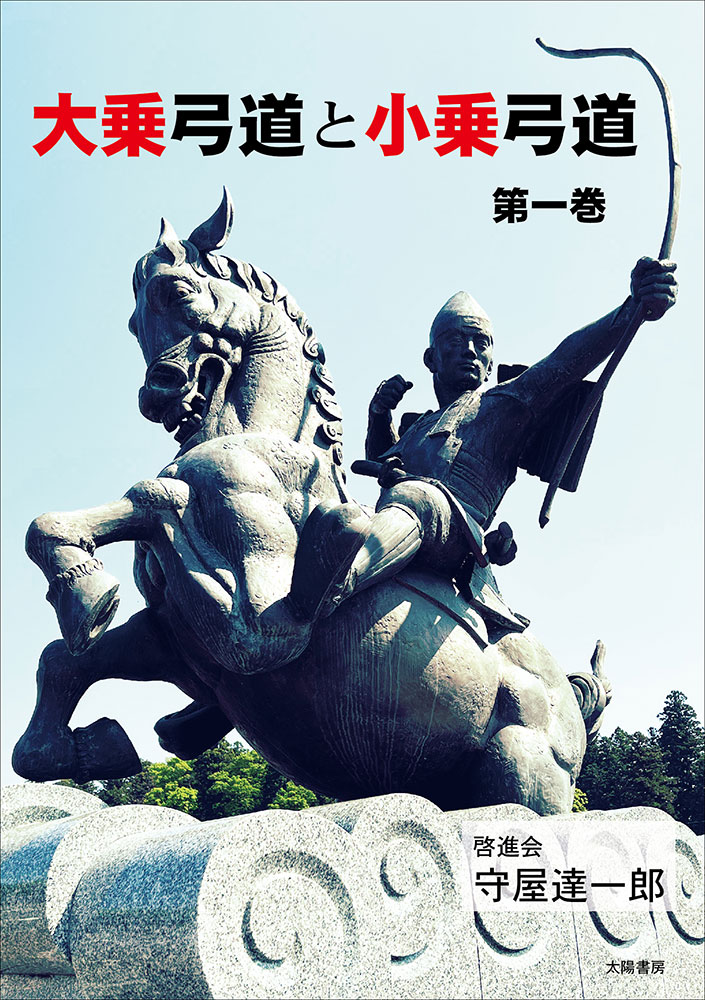

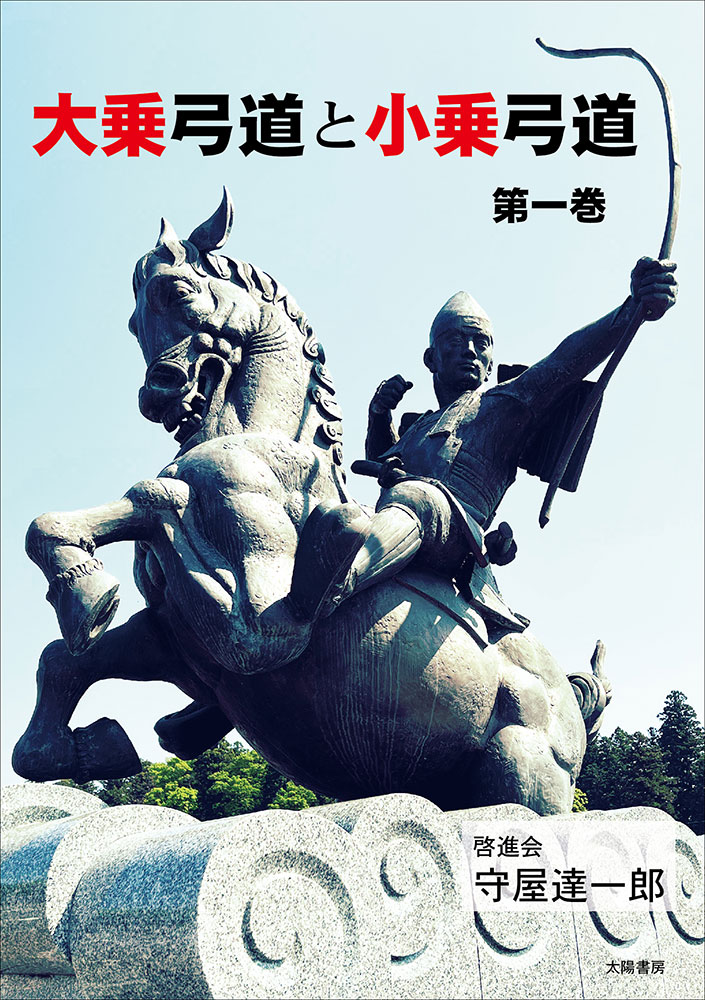
| 作者名 | 作品の分類 | ページ数 |
|---|---|---|
| 守屋達一郎 | 弓道 | 231 |
| 書籍サイズ | 定価(税込) | ISBN |
|---|---|---|
| A5フルカラー | 2,860 | 978-4-86420-328-9 |
| 概要 |
|---|
令和の弓道論、ついに書籍化!『この一冊が、あなたの弓道観を揺さぶる!』――かつて、弓道書はもっと自由で、もっと熱かった。賛否を恐れず独自の論を展開した先達たちの筆は、読む者の射を深く震わせた―― しかし今、弓道の世界から「突き抜けた言葉」は消えかけている。そんな閉塞感に一石を投じるべく始まった『弓道日本』での連載「大乗弓道と小乗弓道」。その第1回から第22回までを収めた、待望の第一巻がついに刊行! 普遍的な弓道=〈大乗〉、個の深みを追求する弓道=〈小乗〉。 この対比から見えてくる、《令和》という時代の弓道の輪郭。 技術でも精神でもなく――そのあわいを縫うように綴られた言葉たち。論文でも、エッセイでもない。だがそのどちらでもある。誰も書かぬなら、自ら書くしかないという覚悟で射られた《論の矢》が、今、読者に迫る。 『射が上手くなるには、書かなければならない!』―― そう言い聞かせながら筆を重ねた著者の十年が、ここに結晶する。 ※本書は季刊『弓道日本』掲載の連載より抜粋・加筆の上編集。 ※副題・図版も新たに整理し、読みやすさと実践性を向上。 |
| 目次 |
|---|
|
はじめに 第1回 序章 ・部活動における大乗弓道 ・啓進会における小乗弓道 第2回 現代弓道のジレンマ ・ジレンマを受け入れる ・ジレンマから不可解へ 第3回 不可解な現代弓道 ・止まらぬ不可解 ・体が嘘を嫌う修練 第4回 修行という方便 ・修行ブーム? ・修行への憧れ ・修行での活性化 第5回 成年弓道家の悩み ・成年弓道家の悩み 第6回 稽古環境作りへの提言 ・自主稽古拡大への環境作り案 第7回 小乗的素引き稽古① ・小乗的素引きのススメ ・小乗的素引きの実践方法(前編) 第8回 小乗的素引き稽古② ・小乗的素引きの実践方法(中編) 第9回 小乗的素引き稽古③ ・小乗的素引きの実践方法(後編) ・まとめ 第10回 小乗的巻藁稽古① ・不名誉な巻藁名人 ・小乗的巻藁稽古のススメ(前編) 第11回 小乗的巻藁稽古② ・小乗的巻藁稽古のススメ(後編) ・まとめ 第12回 斜面打起しと詰合い ・正面打起しだけという弊害 ・斜面打起しのススメ ・恐怖の詰合い修練 ・情識はなかれ 第13回 柔帽子の効用 ・柔帽子のススメ ・それでも迫害される柔帽子 ・柔帽子の遣い方 ・柔帽子から逃げない 第14回 統一体と部分体① ・からだを考える ・皮膚から動く ・統一体のススメ 第15回 統一体と部分体② ・生気論と機械論 ・剛と柔の視点 ・中国武術からの視点 ・居着く部分体 第16回 統一体を生む稽古①―呼吸法― ・呼吸法を学ぶ理由 ・丹田呼吸の基本 ・三呼一吸法 第17回 統一体を生む稽古②―四股― ・四股の重要性 ・稽古の注意点 ・工夫のポイント 第18回 統一体を生む稽古③―腰割― ・腰割の実践 ・稽古の注意点 ・工夫のポイント 第19回 統一体を生む稽古④―体幹回旋― ・体幹回旋による縦線強化 ・稽古の注意点 ・工夫のポイント 第20回 統一体を生む稽古⑤―歩行法― ・歩行の工夫 ・歩行の雑感拾遺 第21回 統一体を生む稽古⑥―站樁功(立禅)― ・站樁功(立禅)のススメ ・稽古の注意点 ・小乗的探索の自験例 ・射術への展開 第22回 統一体を生む稽古⑦―站樁功(馬歩站樁)― ・站樁功(馬歩站樁)のススメ ・稽古の注意点 ・小乗的探の自験例 編集後記 その他主要参考文献 付録:射法八節略解 著者紹介 |